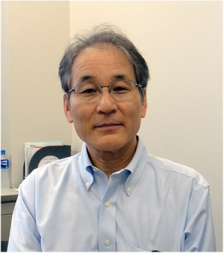
2016年6月10日取材
現在の先生のお仕事の分野にお入りになられたきっかけをお話ししていただけますか?
この分野に入ろうと思ったのは高校生の頃です。元々昆虫とかは好きだったのですが、旧ソビエトの研究者のオパーリンを知ったのをきっかけに生き物の仕組みにすごく興味がでて「生命の起源」といった本を読んだりしました。それでその頃から生き物を化学的に調べるような仕事がしたいなあと思っていました。
先生は医学部出身でいらっしゃいますが、お医者さんというよりは基礎的な研究の方に最初からご興味がおありだったということでしょうか。
そうです。九大に入学して、教養課程を終えて医学部に上がってきたときに、生化学の講義が始まりました。その時、生化学教室の講師をしておられたのが、私の恩師の榊佳之先生です。榊先生の講義を聴いて、夏休みとかに少し実験をしに研究室に出入りしたりするようになったんです。まさに今いるこの教室なのですが、私の4代くらい前になるのかな、ここに榊先生と西郷(薫)先生が講師や助手でおられました。あの頃は多分まだ先生方にも余裕があったのか、学生向けに抄読会とかをやって下さって、それにずっと参加していたという感じでしたね。一応医師免許は取ったんですけどね(笑)。
医師免許を取られてもずっと基礎研究を続けられてきたということですね。
そうですね。ペーパードライバーというかペーパードクターですね(笑)。卒業後はまっすぐ大学院に入ったんです。その頃はクローニング・シークエンス・パブリッシング症候群とか言われた頃で(笑)、組換えDNAが急速に広がっていっている時代だったので、単純にそういうのはあまりやりたくないなと思っていました。それで、榊先生の研究室で、最初は低温室にこもってタンパク質の精製をやっていましたね。転写因子のようなDNAに配列特異的に結合するタンパク質を真核生物から精製しようというのが当時の目的でした。大学院に入ったのが1984年なんですが、まだ精製に関して方法論というのは全然なくて、大学院にいる間に少しずつ出てきたという頃でした。当時は真核生物の転写因子は、Pol IIIの基本転写因子の一つのTFIIIAは確かカエルの卵から取られていたとは思いますけど、いわゆる普通の遺伝子発現を制御するような転写因子はまだ一つもクローニングはされていなくて、核抽出物から結合活性を検出するということでも結構大変な時代でしたね。
1986年くらいから、今でいうゲルシフトアッセイみたいな方法が使えるようになったんです。このアッセイ自体は1970年代からあって、比較的きれいになった大腸菌のタンパク質なんかにはもちろん使われていたんですが、真核生物にはほとんど使われていなかったですね。同じ頃DNA合成が一般的になり始めて、特異的な配列を持ったオリゴヌクレオチドをリガンドとしたアフィニティークロマトグラフィーができるようになってきたんです。私たちもラットの肝臓から、炎症時に合成されるようになる急性期タンパク質の一種をコードする遺伝子の発現を制御する転写因子を精製したんですが、一次構造がうまく決まらなくて。今なら決められると思うのですが、あの当時は難しかったですね。精製しても「アッセイしてSDS-PAGEしたらなくなりました」みたいな感じでしたから(笑)。この因子はIL-6に応答するエレメントに結合するタンパク質で、後に他のグループによってクローニングされ、今ではSTAT3と呼ばれています。その論文を見ると、私たちが私達の遺伝子で同定したIL-6応答配列をリガンドにして、私たちと同じように精製してありました。でも彼らはアミノ酸配列を決められたと(笑)。
その転写因子は私たちが研究していた遺伝子を制御しているだけではなくて、一群の急性期タンパク質の発現にかかわっていたので、「転写因子の機能をちゃんと理解するためには標的遺伝子を全部見つけなければいけない」ということでゲノム全体を見渡す方向に目が行き、そのための方法論を考え始めました。転写因子を潤沢に持っていれば、それを使ってそれが結合するDNA断片をゲノムから集めたかったのですが、精製するので精一杯という状態でした。そこでその代わりに制限酵素を使うことを思いついたんです。制限酵素って2価イオンを除くと標的配列には結合するけれどDNAを切らなくなるので、方法論開発における転写因子のモデルとして使おうとしたわけです。クローニングベクターにマルチプルクローニングサイトがありますよね。それを切り出してきて、そこに働く制限酵素を全部マグネシウム抜きで入れて、ゲルシフトアッセイをすると、みんなそれぞれちゃんと結合するんですよ。この方法を使えば、ゲノム上の結合部位を生化学的に捕まえることができるのではないかと思ったんです。それと、これはゲノムプロジェクト的にもすごく意味があったんです。当時ゲノムを大きく切り分けるということが一つ大事な課題としてあった。制限酵素の中には8塩基を認識するものがあるのですが、このような酵素が切るところはゲノムの地図作りでのマーカーになるんですね。切断部位を跨ぐDNA断片をリンキングフラグメントと言っていたのですが、酵素を酵素としてではなく、結合タンパク質として使ってリンキングフラグメントを決めれば、それはゲノムの解析にも役に立つのではないかと。結局それはうまくはいかなかったのですが、そのことをきっかけにして、その後ゲノムの方に進んだのです。
そのようなことをやっていた頃、1988年にアメリカのコールドスプリングハーバーで初めてゲノムを取り上げたミーティングが開かれたのですが、その時に榊先生がお忙しくて代わりに私が行くことになったんです。当時はゲノムに関する研究がまさに始まるというころで、そこにはいろいろな怪しい人がいっぱい出席していたんです(笑)。
本当に幕開けの頃ですね。
そうなんです。まだストラテジーがない頃なので、いろいろなやり方が提案されて、それらはもちろんほとんどが企画倒れに終わる訳ですが、それがすごく面白くて。それでゲノムの方にますます興味が出てきて、そんな時にアメリカのエネルギー省がUCバークレーにゲノムセンターというのを作ったというのを聞いて、そこに留学することにしたんです。
日本からいらしたら、技術的にはかなり進んでいたのでしょうか?
それがそうでもなくて。ゲノムセンターも始まったばかりだったので、いろいろな問題を抱えていて、すんなりとはいかなかったですね(笑)。いろいろな人が入って来ていて、もちろん中心となるのは生物系の人たちですけれど、情報科学の人たちとか物理化学系の人達とか。私が留学したのはCharles R. Cantorという、もともと生物物理化学の人で、パルスフィールドゲル電気泳動という、ものすごく大きなDNAを分ける電気泳動法を開発した人のところです。彼はエネルギー省の方のゲノムプロジェクトのリーダーだった人で、UCバークレーに隣接するLawrence Berkeley National Laboratoryにヒトゲノムセンターを作るというので、ディレクターとして東海岸のコロンビア大学からバークレーに移ってきたところでした。そこに私が行ったというわけです。ですから、なかなか大変でした(笑)。
どこにいらしても「これから」というところに携わり、ご苦労をされているわけですね(笑)。
おっちょこちょいで目新しいものに飛びついたからでしょうかね(笑)。
でもそのためにいろいろな分野の方やモノに出会う機会がおありだったということでしょうか。
そうですね。それを結構期待していたのですが、残念ながらヒトゲノムセンターの方はちょっと期待外れでしたね。それで、CharlesはUCバークレーの教授でもあったので、キャンパスの方で仕事をしていました。そちらは普通の大学の研究室とあまり変わらなかったです(笑)。まあ、それでもいろいろな分野の人たちと出会ったということは面白かったですね。
バークレーの研究室の方では何をなさっていたのですか?
そこでは大きなDNAを物理的に取ることを目指しました。先ほどお話ししたCharlesのパルスフィールドゲル電気泳動法を使って大きなDNAを分けることはできるのですが、そこから特定の大きなDNA断片を傷つけずに取り出すということは難しかったのです。ハイブリダイゼーション法はDNAを変性させてしまうので使えない。それで、3重らせんDNA(triple helix DNA)というのがあるのですが、それを利用することを考えました。ワトソン・クリックの塩基対の横っちょから3本目の鎖が入ってフーグスティーン型の塩基対形成っていうのを形成すると3本鎖のDNAというのができるのです。3本鎖DNA自体は1950年代からできることは知られていましたが、私たちはそれを利用して、外からオリゴヌクレオチドとか合成DNAを加えて、特定の配列のところにくっつけるということをやりました。2本鎖DNAに人工ヌクレオチドを加えてそのまま酸性状態に置くと3本鎖を形成するんです。例えばオリゴヌクレオチドにビオチンをくっつけておいて、ゲノムDNAに加える。標的配列と3重らせんを作ったところでアビジンを使ってそれを集め、pHを中性に戻すと標的配列が2本鎖DNAとして解離するんです。
なるほど、それで抽出することができるというわけですね。
はい。まあ配列特異的なDNAのアフィニティークロマトグラフィーということで、ハイブリダイゼーションではない抽出法ということです。最終的な目的はもっと大きなDNAを取ることだったのですが、最初は小さなDNAだけれども高い収率かつ非常に高い精製度で取れるようになりました。そして同じことを巨大なDNAに対してもやったんです。巨大なDNAに対してやるときには、DNAが切れないようにアガロースのゲルの中に埋め込んでやるんです。液相中で細胞をつぶすとDNAが切れてしまうので、まずアガロースのブロックに細胞を埋め込んで、その中で膜を溶かして、タンパク質を消化して、ともかく溶液中での剪断力がかからないようにして、メガベースのDNAを取り出すんです。その次に、プローブをつけたビーズをゲルの中に埋め込んでおき、そこに電気泳動されてきたDNAを3重らせんを形成させてトラップし、他のDNAと分離するわけです。まあそのような方法を開発するというようなことをやっていましたね。
その後は?
留学している間に榊先生が東大の医科研に移られたので、私はそこに帰ったんです。その時榊先生から「ゲノム自体の解析というのはこれからもやられていくが、その後のことに目を向けてはどうだ」と言われて、当時よくゲノムの機能解析といわれていたのですが、遺伝子の発現を調べることを始めました。マイクロアレイの走りみたいなことを榊先生のところでも始めておられたのですが、私の性には合わなくて(笑)。それで1992年くらいにLiangとPardeeがディファレンシャルディスプレイというのをやり始めていたので、それを利用してそれのハイスループット化をやってみようかなと思ったのです。ディファレンシャルディスプレイ法というのは、刺激を加えて発現が上がったり下がったりする遺伝子のメッセンジャーRNAをRT-PCRを使って捕まえる方法なのですが、彼らのプロトコルをいろいろといじって、かつ蛍光シークエンサーみたいなものを使って検出できるようにして、スループットが上がるように改良しました。それを使っていろいろなトランスクリプトームを見る、つまり、ディファレンシャルに発現している遺伝子を網羅に捕まえるという仕事をやりました。
その一方で遺伝子からいろいろなタンパク質がわかると、「それぞれのインターラクションをタンパク質のレベルでやりたいなあ。それも大規模にゲノム的にやりたい」と思うようになったんです。それで、ちょうどそのころ酵母2ハイブリッド法というのがだいぶ広まってきていたので、それを網羅的にできないかなあ、と考えたんです。普通は自分の興味のあるタンパク質に結合するものを探すのですが、ゲノムなので「すべてのタンパク質に対して結合するものを取りたい」と考えた訳です。その頃になるとマイクロアレイというのがだんだん流行ってきて、ちょうど運よく日本でも酵母のマイクロアレイを作ろうというプロジェクトができて、九大の農学部におられた久原哲先生がマイクロアレイを作ったんです。久原先生は昔から知っていたので、「どうせPCRで増やすのならフィデリティーの高い酵素で増やしてくれませんか」とお願いして(笑)、増やしてもらったオープンリーディングフレームを全部2ハイブリッド法用の2種類のベクターに入れて、酵母の全タンパク質6000を作れるようにして、その間で総当たりで2ハイブリッドをやるという「タンパク質間相互作用の網羅的な解析」ということをやったんです。
大変な作業ですね。
はい。これができたのは、一つは久原先生とコンタクトがあったからで、もう一つは榊先生の所にいたので理研のゲノムセンターを使うことができた、ということがありますね。タンパク質の組み合わせといっても1つ1つぶつけていたのではとても終わらないので、96個ずつプールにして、プールとプールをぶつけて、生き残ってきたものが持っているプラスミドをシークエンスすることでどのタンパク質とどのタンパク質が相互作用しているのかを明らかにしてゆくわけです。シークエンス自体は、ゲノムセンターがシークエンス工場みたいになっていたのでそこにまかせましたが、その前の段階までは大学院生は入れずに技術員の方2名と私の3人で、サンプルの取り違いなどいろいろな怖い間違いが起こらないような工夫をして注意深くやりました。もちろんこういう仕事ができた大前提には、酵母のゲノムの遺伝子配列が決まっていたということがあります。
この仕事と並行して酵母のタンパク質を使っていろいろなもう少し細かなタンパク質-タンパク質相互作用の研究もしていました。相互作用のドメインというのがあって、その頃に構造生物学の人たちと共同研究をさせてもらいました。その後、ストイキオメトリーというか、Aタンパク質のどのくらいがBタンパク質と結合しているか、という定量的な相互作用解析を、質量分析を使って始めました。こちらの方はそうそう大規模にというわけにはいかないのですが。その頃金沢大学のがん研究所で研究室をもったところだったので、助手の人に産総研の夏目 徹先生の所で1年間質量分析を勉強してもらって、定量プロテオミクスを始めました。この仕事は、東京大学柏キャンパスにできた新領域創成科学研究科に移ってから本格化しました。ハブになるようなタンパク質を落としてくると、一緒にいくつものタンパク質が落ちてくるんですが、それらの量が細胞の状況によってどのくらい変わるかということを定量的に見るんです。そうやって主に酵母を使って機能ゲノムみたいな仕事をしていました。
一方、金沢に移る前、医科研にいた頃に、ディファレンシャルディスプレイ法から面白いことを考え付きました。ディファレンシャルディスプレイ法は、たとえばAさんのメッセンジャーRNAはプライマーの配列がぴったり一致しているのでRT-PCRをすると増えるけれど、Bさんのでは合わないからちょっとしか増えない、というような、転写物の中にある多型の影響を受けることがあるんです。それを利用すれば、体細胞の遺伝子は父方と母方の2コピーあるのですが、その2つの遺伝子にSNP(Single Nucleotide Polymorphism:一塩基多型)の違いがあるとすると、それを見分けることができるのではないかと思ったんです。何でそのようなことを考えたかというと、ゲノムのインプリンティングという現象があって、普通は母方と父方から受け継いだ遺伝子は両方発現するんですが、例えばインスリン様成長因子2(IGF2)は父親からもらった方の遺伝子しか発現しないという風な例外があるんです。そこでディファレンシャルディスプレイ法を利用したら、逆に片一方のアレル(対立遺伝子)しか発現しない遺伝子が取れるのではないかと思ったんです。それでやってみたところ、うまく新しいインプリンティング遺伝子を見つけることができました。インプリンティングがDNAのメチル化と関係していることが明らかになっていたので、それが契機でメチル化を調べるようになったんです。
それでエピジェネティクスの方に入られたわけですね。
そうです。メチル化を調べるといってもインプリンティングの場合には、アレル別のメチル化、つまり父親側のアレルのメチル化状態と母親の方のアレルのメチル化状態を見分ければならないわけです。普通の制限酵素はしばしばメチル化感受性を示しますので、それを利用して調べることが行われていました。しかし、アレル毎のメチル化を明確にするには、普通とは逆にメチル化されないと切れない酵素も併用できるとよいなと思っていたところ、金沢大学にいたころにそういうものが市販されるようになりました。ちょうど榊先生の所で21番染色体の配列が決まってきた頃でした。そこで、CpG アイランドといわれるCG配列が豊富にある領域があるのですけれど、21番染色体上のCpGアイランドについて、片っ端からメチル化感受性とメチル化依存性の制限酵素を使う方法でアレル別のメチル化に差がないかを調べたんです。それがメチル化を網羅的に調べた始まりです。そうやって調べると母親から来たアレルにだけメチル化を示す例が見つかってきて、当初の狙い通りにメチル化のパターンからインプリンティング遺伝子を探せるなということになりました。ところが例外もあって、ある家系でやった時には母親由来のアレルがメチル化されているのに、別の家系で調べると父親由来のアレルがメチル化されている例を見つけたんです。インプリンティングは父親由来か母親由来かという親の性で決まるものなので、これはインプリンティングではない。メチル化の有無が、由来する親の性ではなくて、SNPと連鎖している、配列によって決まっているということを見つけたんです。
その頃、生化学会で先ほどお話しした2ハイブリッド法での網羅的解析、これをインタラクトーム解析というのですが、そのシンポジウムをやりました。そのシンポジウムにCuraGenというアメリカのベンチャーの人を呼んで、ショウジョウバエのインタラクトーム解析の話をして貰いました。すると、最後の5分間で、ちょっと別の話をさせてくれと言いだして、「あなたのラボに大学院生はいるか」と訊いてきたんです。そして「大学院生が一人いれば午後一杯で大腸菌のゲノム配列を決められるぞ」とかいうんですね。何を言い出すのかなと思っていたら、光ファイバーを束ねて切ったものの中でどうのこうのと話し始めたんです。実はそれが、次世代シークエンサーの走りの454という機器のことでした。CuraGenを率いていたのがJonathan Rothbergという人で、この人は私たちが酵母のインタラクトームをやった時のライバルでした。そのRothbergが次に始めたのが454だったわけです
それを聞いて、メチル化を決めるバイサルファイトシーケンスを次世代シークエンサーでやったらゲノム全体を見られるかも、と思ったんです。バイサルファイトシーケンスというのは、DNAをバイサルファイト(亜硫酸水素塩)で処理するとメチル化されていないシトシンは脱アミノ化されてウラシルに変換されるけれど、メチル化されたシトシンは処理の影響を受けないのでウラシルに変換されずにそのまま残るということを使って、バイサルファイト処理をしたものとしていないものの2つのシークエンスを並べてその差異からメチル化シトシンの位置を決める方法です。つまり、元の配列を知っていて、バイサルファイト変換後の配列と並べてみるものなんです。なので、ショットガン的にバラバラに決めたバイサルファイト変換後の配列だけを見て、並べて比較すべき元の配列をちゃんと同定して比較できるのかなと心配になって、当時東大柏キャンパスの新領域創成科学研究科にいた頃だったので、周りにいた情報系の人たちに聞くと「まあ、できるんじゃないかな」と言われて(笑)。ちょうどゲノムネットワークプロジェクトというのが始まるところだったので「やってみようか」ということで始めて、それが今のメチローム解析につながっているんです。
なるほど、ずっとつながっているのですね。
研究に関して情報の人たちと交流をもったのはその頃からなのですか?
それが、僕が初めて情報の人と会ったのは、大学院に入った時なんです。その頃、榊先生は九大の遺伝子施設に居られて、組換えDNAの講習会とかをやっておられました。僕が入った年の夏の講習会では、久原先生が「遺伝子のデータベースの使い方」というような講習会をやっておられました。それに、留学先にも日本から来た女性の情報科学の人がいたんですよ。当時の通産省が第5世代コンピューター(ICOT)プロジェクトをやっていて、ヒトゲノムプロジェクトが始まるというので、そこから派遣されてきた人でした。ゲノムプロジェクトが始まった時からインフォマティクスは大事だということはすごく言われていました。医科研に帰ってきた時には、ゲノムセンターができていて、最初の部門はインフォマティクスでした。というわけで、インフォマティクスの人とはずっと縁があるんです。
ただ、インフォマティクスといっても2つの流れがあるような気がしています。一つは生物物理とか分子進化の系統で、こちらの人たちはたんぱく質の構造をベースとするインフォマティクスで、もう1つはゲノム計画の際に情報科学の方から参入された方々の系統で、こちらは基本的に塩基配列解析なんですよ。この2つはちょっと文化が違うんじゃないですかね(笑)。
情報の中でも異文化交流的なところがあるのですね。
東大柏の新領域創成科学研究科には、医科研ヒトゲノムセンターでご一緒だった高木利久先生が、情報生命科学専攻を全く新たに立ち上げるというので呼んで頂いたのですが、6つある基幹講座のうち僕だけがウエットで後は全部ドライ。だから、色んな意味ですごくいい経験ができました(笑)。更に、インフォマティクスの習得は大学院からだけではだめだということで、高木先生や九大から東大に移られていた西郷先生のご尽力で理学部に生物情報科学科ができて、私は本郷に移りました。
私の場合、仕事の性質上オミックス的なことをやることになります。今は主にメチロームとかエピゲノム関係をやっているので、次世代シークエンサーから出てくるような大きなデータを扱うことになり、どうしてもインフォマティクスが欠かせません。
九大医学部に戻ってからは、情報の人たちと話ができるお医者さんが増えていかなければならないと思ってやっています。それとやっぱり医学を学んでいる人たちの中からベイシックなサイエンスをやる人を育てたいという思いがありますね。
最後にPDIS事業にかかわってこられて、支援と高度化に関してご意見やご感想はございますか。
PDISには機能ゲノミクス領域として3年前から参加しました。いろいろな先生方の支援をやってみて思うのは、実験もそうですが情報解析がやっぱり大変ですね。一応定型的な解析はやるのですが、それぞれの先生で目的が違うので、どうしてもカスタマイズということになる。定型的な解析までは支援でいいのですが、高度な解析になると支援と高度化というか共同研究の区別が難しくなるんですね。
私たちとしては、PDISの中で自分たちのメチローム解析の技術を高度化したいですし、それを皆さんに使っていただけるというのはうれしいことなんです。私なんかは、いろいろな方法論を作るのが好きでずっとやってきていますけれど、それって、いろいろな人に使ってもらいたいというのがありますね。それを使って自分が何かを見つけるだけではなくて、他の人がいろいろなことを発見するきっかけになるというのが嬉しい。
もうひとつPDISで厄介だったのは、扱うものに臨床サンプルがあることなんです。まず、臨床サンプルは倫理審査を受けなければならない。もちろんサンプルを持ってくる先生方は所属機関の倫理審査を通ってから持ってこられるのですが、支援をする私たちの方も九大で倫理審査を受けねばならず、それがちょっと面倒くさい。それと臨床サンプルの場合には、純度や量の問題があります。私たちは精度の高い解析を目指してこれまでやってきたのですが、臨床サンプルの中にはそれだけの精度が出せないようなものもあります。きれいなサンプルで高い性能を出すという形の高度化とは別に、汚いサンプルに強いという形の高度化も必要なのかなと思いました。最後に、臨床検体で得られたデータは、個人ゲノムみたいなものなので、取り扱いに気を遣う必要が出て来ます。
それと、予算。シーケンス予算は潤沢にあると聞いていたので、いろんな方に応募をお勧めしました。でも全メチローム解析は金食い虫なので、2年目からはサンプル数に制限をかけざるを得なくなったのがちょっと残念でした。そこで、費用対効果の大きい標的メチローム解析の技術を高感度化して提供し、そこを補ってきました。
まあ色々な問題があるにせよ、PDISのような活動は、研究者が必要に応じて高度な技術を自身の研究に取り入れられるので、必要な仕組みだと思いますね。
解決しなければならない難しい問題もあるけれど、継続することで乗り越える方法が見えてくるということでしょうか。この度はいろいろな興味深いお話をありがとうございました。